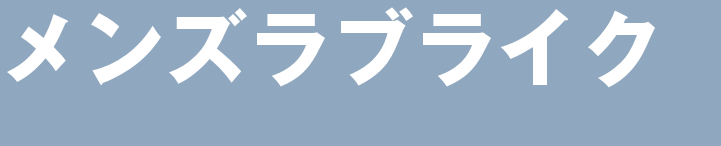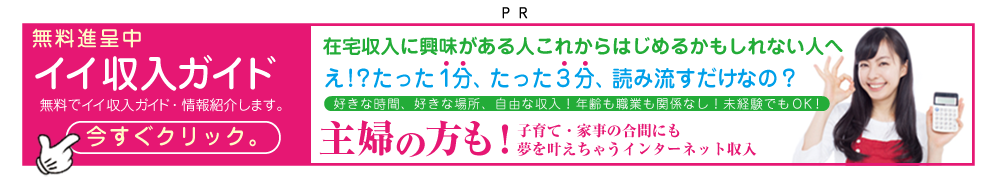今回は川越城と佐倉城をご紹介します。
川越城
主な遺構は、本丸御殿、家老詰所、富士見櫓跡、中ノ門堀跡、土塁です。
川越城は扇谷上杉(おうぎがやつうえすぎ)の家宰太田道真・道灌(どうかん)父子が築城したことに始まりました。
江戸入府後にこの城を重視した徳川家康は、譜代の家臣を入城させました。
大改修が行われたのは松平信綱(まつだいらのぶつな)のときで、信綱は城域を拡大して近世城郭に変貌させるとともに、城下町を整備しました。
遺構は別記のように少ないですが、城下町のたたずまいは今も残っています。
御殿近くの三芳野(みよしの)神社は、童歌「とおりゃんせ」発祥の地と伝わっています。
・中ノ門堀跡
敵の進路を阻むように組み合わせた3つの堀のうちの1つ。2009年に構築当初の規模(幅18m、深さ7m)及び勾配に整備されました。
・富士見櫓跡
富士見櫓は三重三階または二重二階だったと推定されています。城中では最大の櫓で天守代わりに使われていました。
・本丸御殿
豪壮な大唐破風屋根の車寄せ(玄関)をそなえ、内部の大広間などが一般に公開されています。御殿の棟続きに家老詰所も移築復元されています。
スタンプ設置場所 川越城本丸御殿受付窓口
佐倉城
主な遺構は、天守台、堀、土塁、角馬出(かくうまだし)、出丸跡です。
佐倉城は石を一切用いず、土塁と深い空堀、そして水堀で守られた土づくりの近世城郭です。
椎木門(しいのきもん)跡の前面にある角馬出は、発掘調査を基に復元されていてその威容を実感できます。
また、湿地帯に掘られた水堀が本丸台地を巡り、本丸の南北には馬出のように突き出した出丸が構築されています。佐倉城主は幕府中枢を占めた者が多かったこともあってか、豪壮な殿舎や櫓などの存在をうかがわせる遺構もあります。
・水堀と出丸
残存状態がよく、見て回れば枡形状になっているのがわかります。
・天守台と土塁
天守台はその後方の土塁とセットになっていて、三重の天守は1階の一部が土塁に懸っていたといいます。
・角馬前面の空堀
国立歴史民族博物館前、三の丸北側に巨大な角馬出が復元されています。かつては現在よりももっと深い空彫りだったそうです。
スタンプ設置場所 佐倉城址公園管理センター、国立歴史民族博物館
ふくすけ
最新記事 by ふくすけ (全て見る)
- 夢や目標を叶える方法 - 2025年3月24日
- トレンディアフィリエイト教材「下剋上∞」 - 2025年3月24日
- 成功する決意 - 2025年3月23日