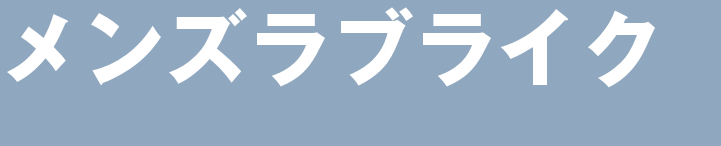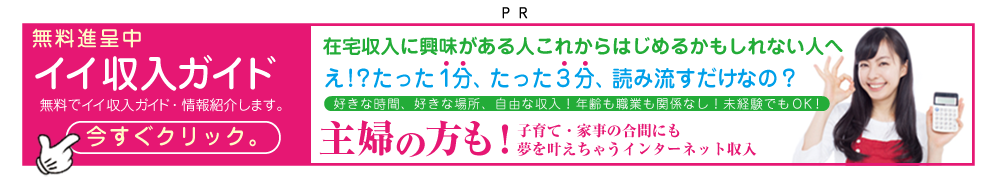東福寺の大伽藍(だいがらん)は、三門を正面に、法堂(はっとう)、方丈が直線状に並ぶ禅宗様式の伽藍配置になっております。
そして、法堂のすぐ傍らには、修行僧達の寝泊りする禅堂(ぜんどう)が建てられています。
なぜ、この禅堂が境内のど真ん中に建てられているかと言いますと、東福寺は参拝者を迎え入れるための物ではなく、修行僧達が修行をするために建てられているので、効率よく動けるようにど真ん中にあるみたいです。
それから、禅堂の隣に建つ東司(とうす)と呼ばれる建物があります。
これは、修行僧達が使っていた、今でいうお手洗いです。
別名は、百雪隠(ひゃくせっちん)と呼ばれ、まさに百人ができるとても大きな建物です。
この百雪隠を使うのにも、いろいろなルールと手の洗い方まであったそうです。
やはり、修行は大変ですね。
法堂(はっとう)には、大涅槃図(だいねはんず)が掲げられておりますが、公開期日があります。
大涅槃図とは、お釈迦様が亡くなられた時の様子を描いた絵です。
その大涅槃図を描いたのが、画僧として東福寺に仕えた、吉山明兆(きっさんみんちょう)です。
そして大涅槃図が、そのころ東福寺と関わりが深かった、室町幕府第4代将軍・足利義持(あしかがよしもち)が非常に感銘を受けて、明兆に絵の褒美として何か望むことはないかと言われた時に、明兆は東福寺にある桜の木を伐採するようにお願いしました。
なぜかと言うと、境内に桜の木があった時は、たくさんの人が集まって来てお花見をすることが多かったのですが、東福寺は本来、禅のお寺で修行僧が日々修行をしていたので、その光景を見てしまうと心が動揺してしまい、修行の妨げになると常々懸念されていたので、それを聞き入れられて、桜の木が全部伐採されて紅葉だけが残ったと言うことです。
しかし、桜の木がなくなり本来の修行の場として静けさを取り戻したのも束の間、江戸時代に当時の観光ガイド本であった、都名所図会(みやこめいしょずえ)が出版されると、くしくも東福寺は紅葉の名所として脚光をあびるようになりました。
静けさを望んだ明兆さんには、ちょっとつらいですね。
でも、現在では京都屈指の紅葉の名所になっており、東福寺の中でも最大の見どころとなっているのが通天橋(つうてんきょう)です。
長い橋で紅葉が左右いっぱいで、とても綺麗です。
とくに、橋の中央部にある張り出し部分から見下ろす洗玉澗(せんぎょくかん)が絶景です。
また行く機会があれば、是非、見に行ってください。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
nuts
最新記事 by nuts (全て見る)
- インターネットで継続して稼ぐ方法とは! - 2020年11月28日
- 世界遺産として登録されている京都の下鴨神社! - 2020年11月23日
- スピード成功するのに必要なメゾットとは! - 2020年11月17日