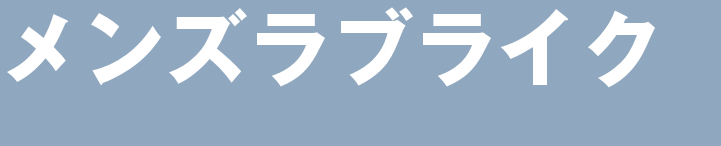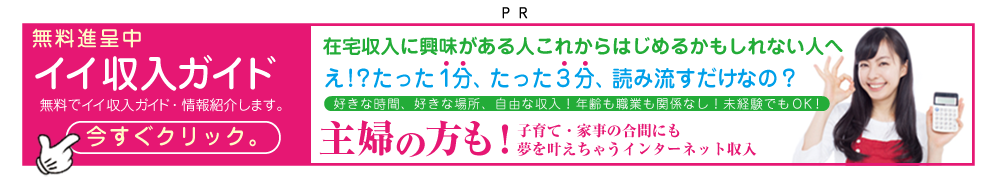今回は岐阜城と山中城をご紹介します。
岐阜城
主な遺構は天守台、櫓台跡、門跡、石垣です。
見どころは、もとは稲葉山城と称され、鎌倉時代に二階堂行政が築城したと伝わるが、詳細は不明です。
確かなことは、戦国時代に斎藤道三が山城と城下町を整備したことです。
斎藤氏は三代にわたり居城しましたが、織田信長によって追放されました。
信長は町の名を「岐阜」と名を改め、山頂の城と山麓居館の改修を行いました。
現在、山麓部分は岐阜公園として整備されており、信長の居館跡ばどを見学できます。
また、登山道を歩けば、石垣や曲輪跡を見ることができます。
・長良川越しに見た岐阜城
岐阜城は標高329mの金華山(稲葉山)山頂に築かれた典型的な山城です。
これほどの山城が鎌倉時代初めに築かれることはないという見方から、斎藤道三の築城と考えられています。
・織田信長居館跡の巨石粗
岐阜公園の一部に通路や石組が整備復元されています。
他に水路、井戸、石垣などもあります。
・山頂の天守
天守は昭和31年(1956)に鉄筋コンクリートで再建されたものです。
三重四階の展望台からの眺望はすばらしいです。
スタンプ設置場所 岐阜城(入場者に限る)
山中城
主な遺構は、障子掘、土塁です。
見どころは、山中城は戦国時代末期に小田原北条氏と豊臣秀吉の兵が激突した城です。
この城の特徴は、石垣のない土造りの城であることと、複列型障子堀(障子堀)、単列型障子堀(畝堀)を巧みに各曲輪の周囲に配して、防御能力を高めていることです。
すでに発掘調査に基づいて復元整備されているので、誰でも障子堀を実現できます。
また、現地で見ることによって小田原北条氏流築城術のノウハウを知ることができます。
・二ノ丸虎口と築橋
手前が二ノ丸虎口で、土塁を枡形状にしています。
橋下は深い空堀です。
・単列型の障子堀(畝掘)
堀が直交する形で田の畝のような形をした障壁を設けています。
畝が堀内を自由に移動することを防ぎます。
・複列型の障子堀
障壁を組み合わせて、複数の衝立障子のような障害物を設けた堀になっています。
スタンプ設置場所 山中城跡売店前
ふくすけ
最新記事 by ふくすけ (全て見る)
- 夢や目標を叶える方法 - 2025年3月24日
- トレンディアフィリエイト教材「下剋上∞」 - 2025年3月24日
- 成功する決意 - 2025年3月23日